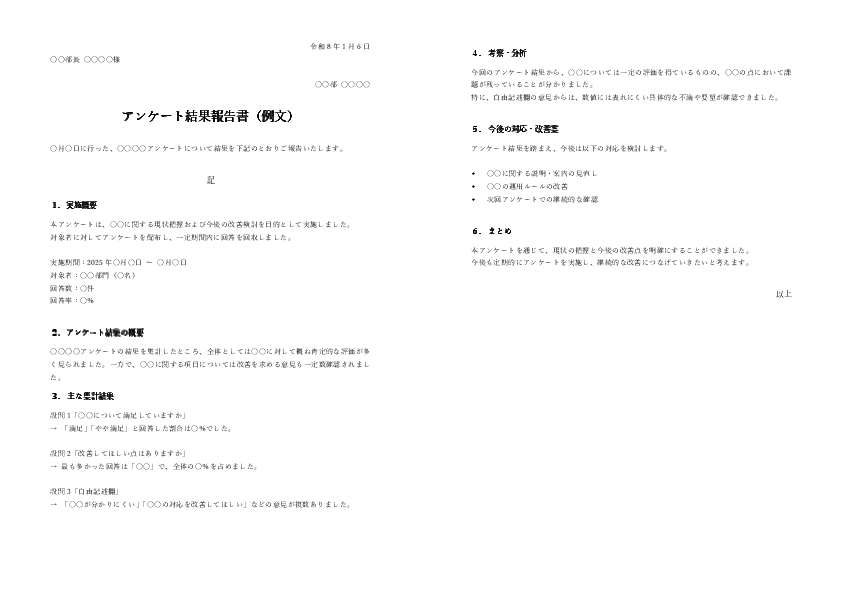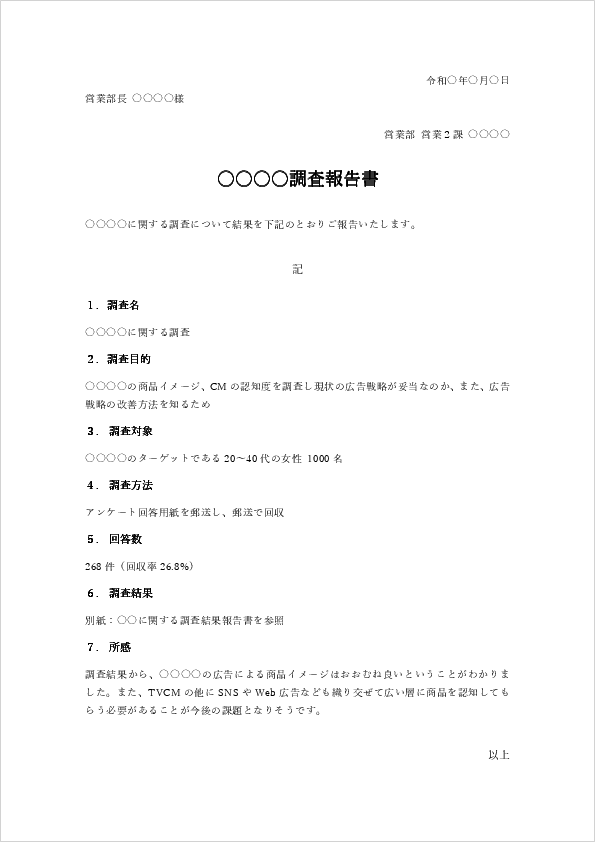このページでは、アンケート結果報告書(Word)、調査報告書を例文付きで紹介します。
筆者が、業務で商品満足度、セミナーアンケートなどの報告書を多数作成した経験から実務でそのまま使えるように解説するので、アンケート報告書をすぐに作りたい方は参考にしてください。
この記事ではアンケートの結果を集計・分析し、施策へつなぐ報告書用です。日報や作業報告書、調査企画書などの事実経過の報告や計画の立案は対象外です。
アンケート用紙(設問票)テンプレートは関連記事でご案内します。
アンケート用紙テンプレート
アンケート結果報告書テンプレート(例文付き)
社内アンケートや満足度調査の結果をまとめる際に使える汎用的なアンケート結果報告書の例文付きテンプレートです。
実施概要・調査結果・考察・今後の対応までを整理し、上司や関係部署へ分かりやすく報告できる構成になっています。
このテンプレートの特徴
- アンケート結果を文章+箇条書きで整理できる
- 数値だけでなく考察・所感まで記載できる
- 次回対応・改善点を明確にできる
記載項目と例文
1.実施概要
本アンケートは、〇〇に関する現状把握および今後の改善検討を目的として実施しました。
対象者からの回答を集計し、結果を以下のとおり報告します。
- 実施期間:2025年〇月〇日 ~ 〇月〇日
- 対象者:〇〇部門(〇名)
- 回答数:〇件
- 回収率:〇%
2.アンケート結果の概要
アンケート結果から、全体としては〇〇について概ね良好な評価が得られました。
一方で、〇〇に関しては改善を求める意見も見られ、今後の検討課題であることが分かりました。
3.主な集計結果
主な設問に対する回答結果は以下のとおりです。
- 設問1「〇〇について満足していますか」
→「満足」「やや満足」と回答した割合は〇%でした。 - 設問2「改善してほしい点はありますか」
→ 最も多かった回答は「〇〇」で、全体の〇%を占めました。 - 設問3(自由記述)
→ 「〇〇を改善してほしい」「〇〇が分かりにくい」などの意見が寄せられました。
4.考察・分析
今回のアンケート結果から、〇〇については一定の評価を得ているものの、
〇〇の点において改善の余地があることが明らかになりました。
特に自由記述の内容からは、数値には表れにくい具体的な課題が確認されました。
5.今後の対応・改善案
アンケート結果を踏まえ、今後は以下の対応を検討します。
- 〇〇に関する運用・対応方法の見直し
- 〇〇の情報提供・周知方法の改善
- 次回アンケートによる効果検証
6.まとめ
本アンケートを通じて、現状の課題と今後の改善方向を整理することができました。
今後も継続的にアンケートを実施し、業務改善につなげていきたいと考えます。
※ 本テンプレートは例文のため、実際の調査内容や数値に合わせて編集してください。
調査報告書テンプレート(例文付き)
広告効果測定、顧客満足度調査、イベント満足度調査などで幅広く使えるアンケート結果報告書の例文付きテンプレートです。
調査名・目的・対象・方法・回収率・結果・考察・今後の対応まで、社内提出に必要な項目を一通り整理しています。
このテンプレートでできること
- 調査結果を定型フォーマットで整理できる
- 数値・回収率・所感を上司向けに簡潔に報告できる
- 広告・施策の次回改善アクションまで明確にできる
記載項目と例文
1.調査名
〇〇に関するアンケート調査
2.調査目的
〇〇商品のイメージや広告の認知度を調査し、現状の広告戦略が適切かを確認するとともに、
今後の改善方針を検討するために実施した。
3.調査対象
〇〇をターゲットとする20~40代の女性 1,000名
4.調査方法
アンケート用紙を郵送し、郵送にて回収した。
5.回答数・回収率
268件(回収率:26.8%)
6.調査結果
調査結果の詳細については、別紙「〇〇に関する調査結果報告書」を参照。
7.所感・考察
調査結果から、〇〇の広告による商品イメージは概ね良好であることが確認できた。
一方で、認知経路についてはテレビCM以外の媒体での接触が少なく、
SNSやWeb広告を活用した情報発信が今後の課題であると考えられる。
8.今後の対応・改善案
- SNS広告・Web広告を活用した認知拡大
- 次回調査時の設問内容の見直し
- ターゲット層別の効果測定の実施
このテンプレートが向いているケース
- 広告効果・CM効果の測定結果をまとめたい場合
- 社内向けにアンケート結果を正式文書で提出する場合
- 簡潔に「結果+所感+次の施策」を伝えたい場合
※ 数値や調査対象は仮置きのため、実際の調査内容に合わせて編集してください。
アンケート結果報告書とは
アンケート結果報告書とは、アンケートで得たデータを整理し、意思決定に必要な結論と施策案を入れた文書です。
「誰に」「どんな方法で」「どれくらいの数を集めたか」といった前提を書き、質問ごとの答えを整理し、満足度などの数字の変化を確認します。
アンケート結果報告書のまとめ方
アンケート結果報告書では、集計した数値や意見をそのまま並べるのではなく、目的に沿って要点を整理し、読み手が判断しやすい形にまとめることが重要です。以下では、そのまま使える基本的なまとめ方の流れを解説します。
1. 表紙・サマリー(エグゼクティブサマリー)
5〜10行で結論と推奨アクションを先に提示します。背景や手法の詳細は後段に回し、意思決定者が最初の1ページで全体像を把握できるようにします。
2. 調査概要
何を明らかにするための調査か、対象商品名や期間を入れて明確にします。
調査目的
仮説や検証したい指標を簡潔に記載します。例:値上げ後の満足度低下の有無を確認します。
調査対象
年代、性別、購入有無、居住エリア、会員区分などのスクリーニング条件を明記します。
調査方法
ウェブ、対面、郵送、会場調査など。調査期間、配信数、回収数、回収率、重み付け有無を含めます。
有効回答・母数
有効サンプル数(n)を設問ごとに記載します。フィルターによりnが変動する場合は注記します。
3. 主要指標サマリー
満足度、NPS、再購入意向、推奨意向、継続意向などKPIを一覧化します。前回比較や目標値とのギャップも併記します。
4. 設問別結果(単純集計)
各設問の分布を棒グラフや円グラフで示します。項目数が多いときは上位・下位項目に絞り込みます。
5. クロス集計と差の検定
性別×満足度、年代×推奨意向、購入頻度×不満要因などでクロスします。必要に応じてカイ二乗検定、t検定などの差の有意性を注記します。
6. 自由回答の要約(テキストマイニングの要点)
頻出語、共起語、ポジ・ネガ分類、代表コメントを提示します。生の引用は要点を保ったうえで匿名化します。
7. インサイトと原因仮説
集計結果から読み取れる要因を仮説として整理します。例:配送遅延が定期便の継続意向を押し下げています。
8. 結論・施策案・優先度
優先度、期待効果、コスト、リードタイム、担当を明記します。短期施策と中長期施策を分けると実行に移しやすくなります。
9. 次回に向けた改善(設問・配信設計)
設問の冗長削減、選択肢の粒度調整、サンプリングの偏り是正、回収率向上策を記載します。
グラフ選定とデータ品質の基本
アンケート結果をまとめるときは、ただ数字を並べるよりもグラフにしたほうが分かりやすくなります。ここでは初心者の方にも分かりやすいように、グラフの選び方とデータの扱い方の基本を紹介します。
グラフ選定の目安
→ 棒グラフ
・時間の変化を見せたいとき
→ 折れ線グラフ
・全体の内訳を示したいとき
→ 100%積み上げ棒グラフ
・満足度など「賛否の分布」を見せたいとき
→ ダイバージング棒グラフ
・円グラフは3〜5項目までに絞ると見やすくなります
指標の扱い
・満足度(5段階評価)は平均値だけでなく「とても満足+満足(Top2Box)」や「不満+とても不満(Bottom2Box)」の割合も示すと理解しやすいです
・NPS(ネットプロモータースコア)は「推奨者%−批判者%」で計算します。報告書に計算式を添えると親切です
信頼性の表記
報告書には次の情報も添えると、数字に根拠があると伝えられます。
・回答率(回収率)
・欠損(無回答)があるかどうか
・重み付けをしたかどうか
・自由回答をどう抽出・整理したか
さらに詳しく伝えたいときは、信頼区間や統計検定の結果を脚注に入れると専門的にも信頼されやすくなります。
記入例(要約版)
アンケート結果報告書は「数字の結果」だけでなく、「そこからどんな結論を出せるか」「次に何をすべきか」を書くことが大切です。ここでは一例として、分かりやすい要約の形を紹介します。
結論
配送にかかる時間(リードタイム)が、顧客満足度や継続して利用したい気持ちに大きく影響しています。倉庫を増やして配送を早めれば、満足度(Top2Box)が5ポイント改善する見込みです。
推奨アクション(90日計画)
2. 配送に関する問い合わせを減らすため、FAQページの整備や自動音声案内の改善を行う
3. 定期購入の利用者に対して、万一遅れた場合に使えるクーポンを試験的に導入する
よくある質問(FAQ)
まとめ
この記事では、アンケート結果報告書、調査報告書の書き方やテンプレートについて紹介しました。
アンケート結果報告書は、結果が見てすぐにわかるようにポイントを押さえつつ簡潔に作成する必要があります。
項目や書き方は、ある程度決まっているのでテンプレートを参考にしながら簡潔で見やすい調査報告書を作成してください。